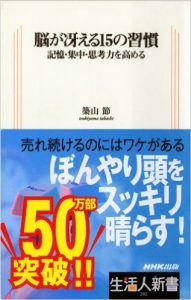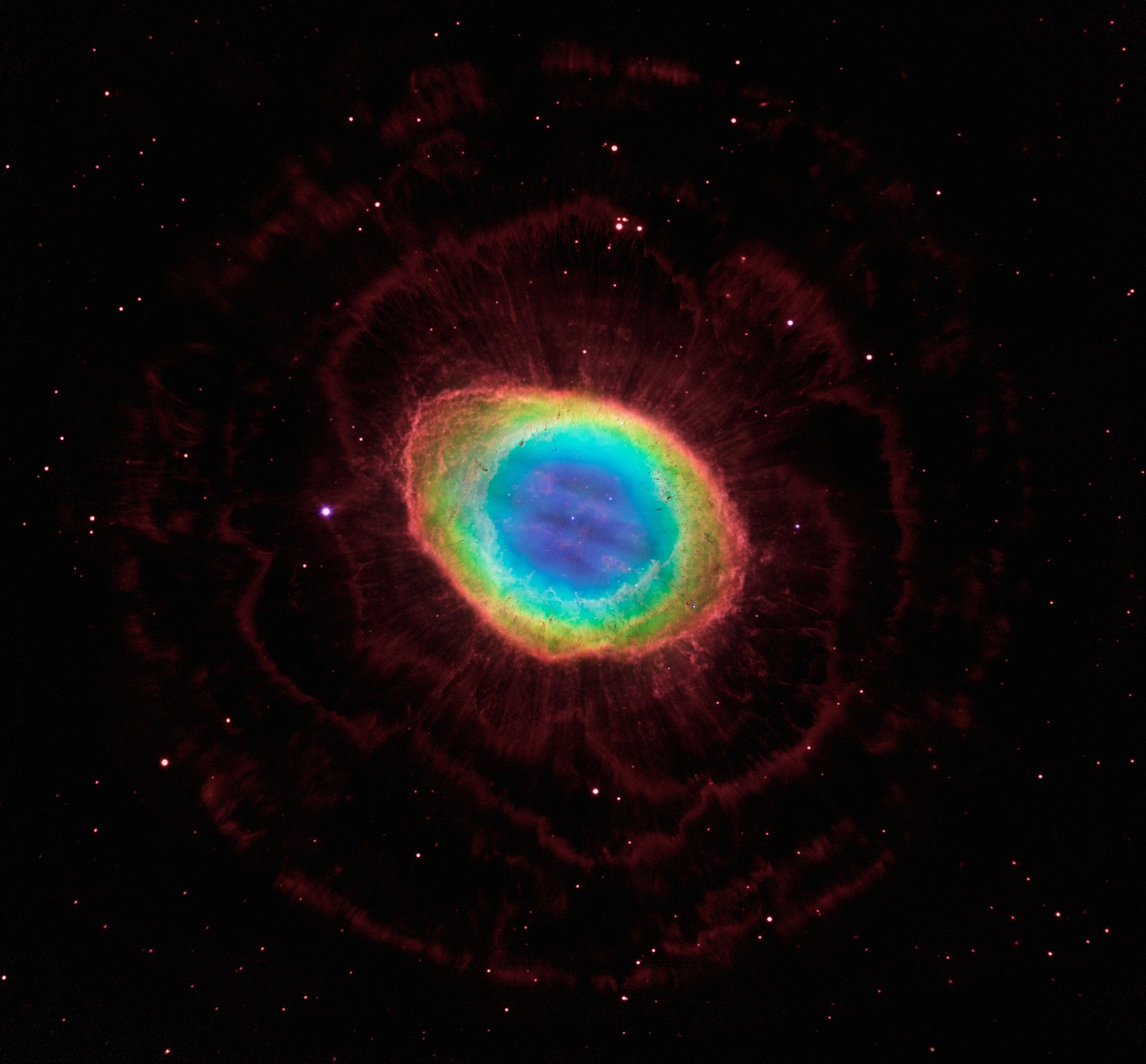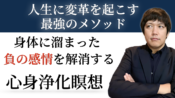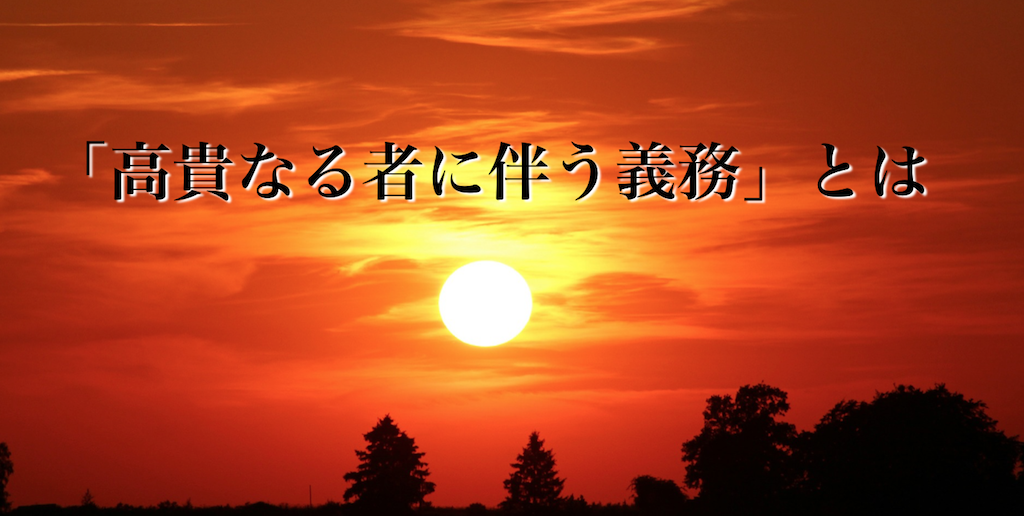【脳=思考を整える】「脳が冴える15の習慣」
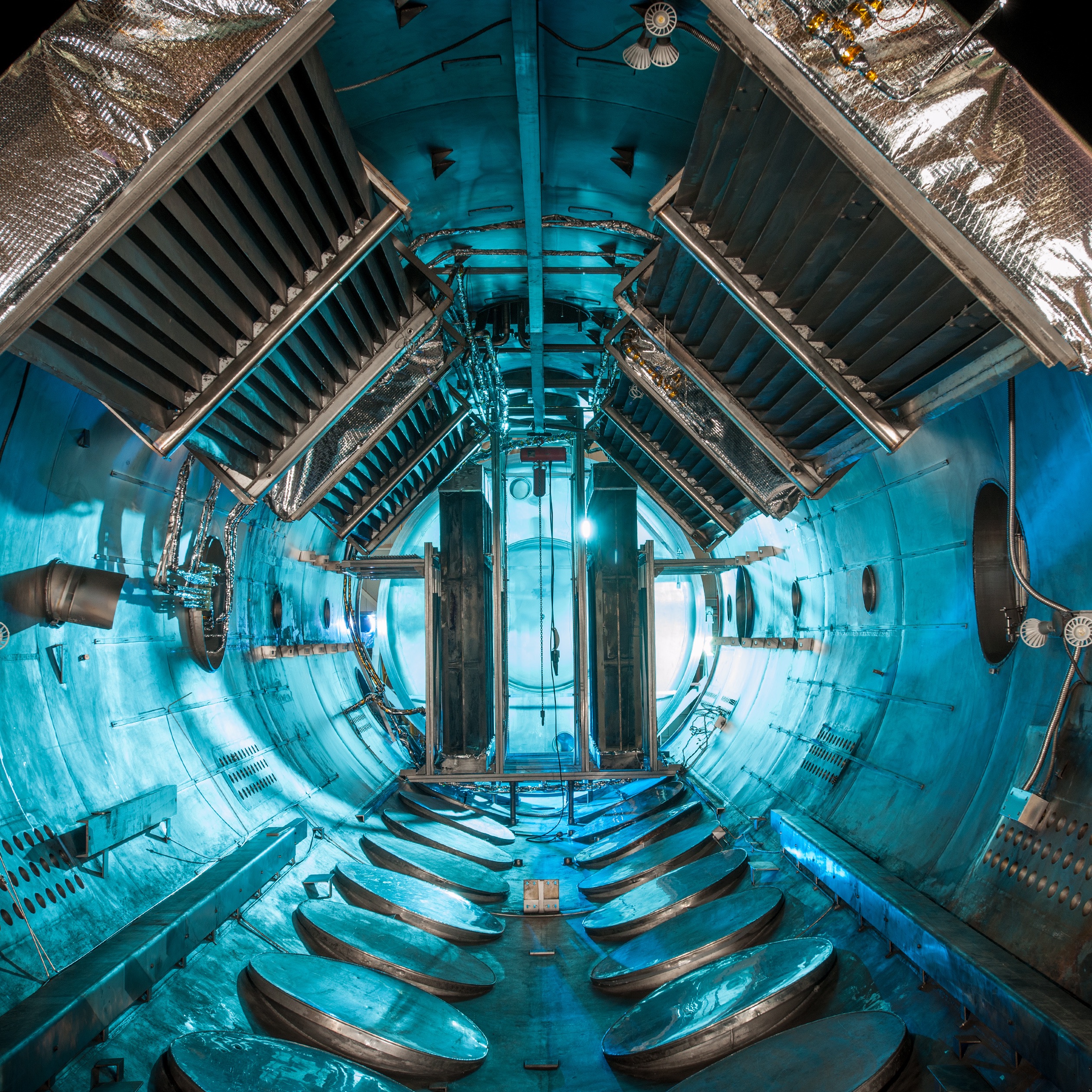
今回ご紹介させていただくのは、
脳神経外科専門医の築山節先生の著書
「脳が冴える15の習慣」である。
築山 節 (著)
内容(「BOOK」データベースより)
最近、何となく頭がぼんやりしている―。記憶力や集中力、思考力が衰えたように感じている。そんな「冴えない脳」を治すために必要なのは、たまに行う脳トレーニングではなく、生活の改善である。『フリーズする脳』で現代人の脳に警鐘を鳴らした著者が、すぐにでも実行できて、有効性が高い15の習慣を提案。仕事ができる脳、若々しい脳を取り戻すためのポイントを分かりやすく示す。
人間は「思考する動物」である。
では、その「思考」が何によって行われるかというと、
もちろん、誰もが「脳」と答えるだろう。
私達は、進化の過程で高度に発達した「脳」を使って思考し、行動する。
しかし、多くの人が忘れてしまっているのではないだろうか?
「脳」も、心臓や肺、胃、腸と同じ
「臓器」の1つであるということに。
「思考」は人間の「脳という臓器」の活動なのだから、
当然、脳の状態であったり、コンディションの良し悪しによって、
パフォーマンスに大きな差が生まれる。
人はどこかで「自分の思考は、常に安定したものである」という認識を持っている。
「一貫したものである」という認識を持っている。
しかし、例えば40度の高熱を出したらどうなるだろう?
脳は疲弊し、思考どころではなくなるだろう。
多くの人が、自分の健康状態がどれほど「思考」に影響を及ぼし、左右するかということに、
無頓着すぎるのではないだろうか?
例えば、多くの人が「夜更かし」をする。
現代社会を生きていく上で、それは仕方ない部分もある。
どんな真夜中でも、街灯が明るく照らしているし、
24時間営業のコンビニもあるし、飲食店もある。
しかし「夜更かし」や「睡眠不足」が、
脳の活動にどれほどの影響を及ぼすかについては、
自覚的であるべきである。
毎日多くの時間を、パソコンやスマホ、テレビを見て過ごす。
それが、脳の活動にどれほどの影響を及ぼすかについては、
もっと意識的であるべきである。
そういった生活を続けていると、やがて「脳の機能」が低下していき、
- 話しかけられた時に、パッと反応できない
- 本や新聞を読んでも内容が頭に入ってこない
- 覚えていたことを「ド忘れ」する
- 思考がすぐに途切れる
- 集中力が続かない
- すぐにボンヤリしてしまう
- 情緒不安定になる
といった「弊害」に悩まされることになる。
自分で自覚し、意識的でいることで、対処することができる
本書では、筆者が脳外科医として「ボケ症状」の治療に取り組んできた経験に基づいた、
脳のコンディションを整え「思考」のパフォーマンスを最大限に発揮する為の、
「15の習慣」について書かれている。
- 習慣1 「生活の原点をつくる」 脳を活性化させる朝の過ごし方。足・手・口をよく動かそう
- 習慣2 「集中力を高める」 生活のどこかに「試験を受けている状態」を持とう
- 習慣3 「睡眠の意義」 夜は情報を蓄える時間。睡眠中の「整理力」を利用しよう
脳の活動を安定させ、集中力や頭の回転の速さを高めたりするための習慣。
- 習慣4 「脳の持続力を高める」 家事こそ「脳トレ」雑用を積極的にこなそう
- 習慣5 「問題解決能力を高める」 自分を動かす「ルール」と「行動予定表」をつくろう
- 習慣6 「思考の整理」 忙しい時ほど「机の片付け」を優先させよう
思考系の中枢である前頭葉を鍛えたり、その力が発揮されやすい環境を整えたりするための習慣。
- 習慣7 「注意力を高める 」 意識して目をよく動かそう。耳から情報を取ろう
- 習慣8 「記憶力を高める」 「報告書」「まとめ」「ブログ」を積極的に書こう
情報を脳に入力する力と記憶力を高めるための習慣。
- 習慣9 「話す力を高める」 メモや写真などを手がかりにして、長い話を組み立てよう
- 習慣10「表現を豊かにする 」 「たとえ話」を混ぜながら、相手の身になって話そう
情報を出力する力、つまりコミュニケーション能力を高めるための習慣。
- 習慣11「脳を健康に保つ食事 」 脳のためにも、適度な運動と「腹八分目」を心がけよう
- 習慣12「脳の健康診断 」 定期的に画像検査を受け、脳の状態をチェックしよう
臓器としての脳を健康に保つための習慣。
- 習慣13「脳の自己管理」 「失敗ノート」を書こう。自分の批判者を大切にしよう
- 習慣14「想像力を高める 」 ひらめきは「余計なこと」の中にある。活動をマルチにしよう
- 習慣15「意欲を高める 」 人を好意的に評価しよう。時にはダメな自分を見せよう
応用編。習慣13は脳を自己管理する方法。習慣14は「ひらめき」を生み出しやすくする習慣。習慣15は意欲を高めやすくする生き方について。
時間的にも経済的にも負担にならない、
老若男女、誰にでも簡単に実践できるものである。
本書の一文を引用する。
脳にとって良い習慣を身につけることは、木を育てることに似ています。豊かな葉を繁らせる木でも、環境と育て方が悪ければ葉が落ちる。それが脳で言えば、機能が衰えたり、上手く使えなくなったりするということです。そのとき、何か特殊な方法で一時的に回復させることができたとしても、長続きしません。環境と育て方に原因があるわけですから、時間が経てばまた枯れていきます。大切なのは、その原因を解消することです。脳で言えば、生活を改善する必要があります。だからといって、すべてを変える必要はありません。いくつかの有効な習慣を身につけるだけでいいのです。それを身につけたからといって、すぐに劇的な効果が現れるとは限りませんが、その効果は一生続く。じわじわと脳の働きを高め、仕事ができる脳、若々しい脳を取り戻せていきます。そのための指針を示すのが本書の趣旨です。
「本書で書かれていることを、すべて律儀に実践する必要はない」と、筆者は言う。
ただ「脳の性質」や「脳の機能を向上させる方法」を知ることで、
自分で脳のコンディションを整え、対処することができる。
「自分で脳に良い影響を与える能力」を身につけることができる。
それはすなわち、
「人生を豊かにするスキル」ともいえる。
当ブログのテーマである、
「自分の人生を自立的に生きる」という目的にも、合致するものである。
全ての物事が過度に効率化され、便利過ぎるともいえるこの現代社会で、
ともすれば、無自覚のまま脳の機能を衰えさせてしまわぬよう、
気を付けていきたいものだ。
明日は明日の風が吹く。