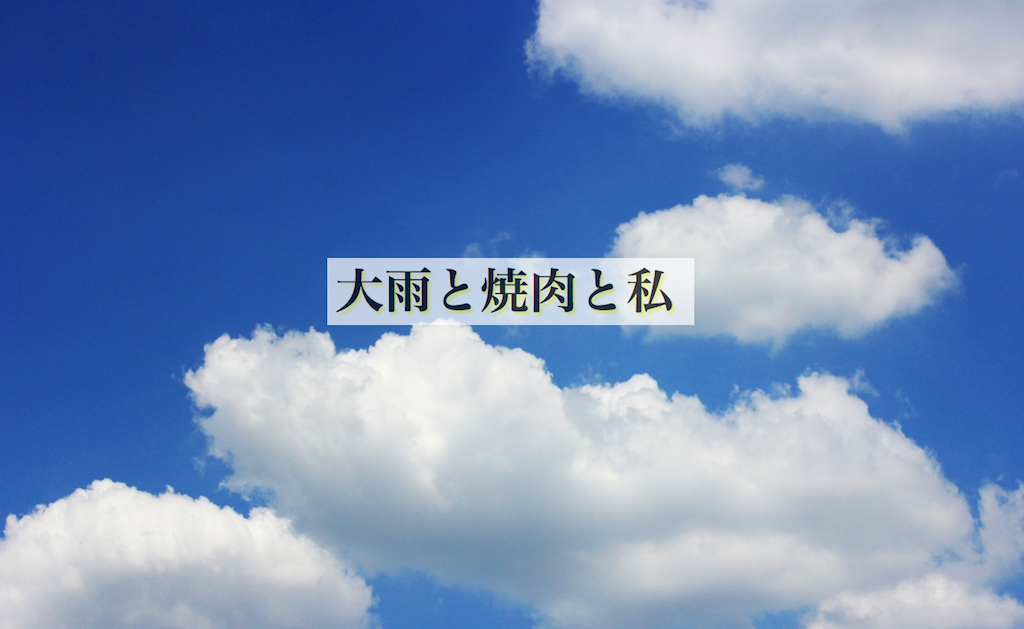「物をよくなくす人」の特徴・性格と4つの対策方法
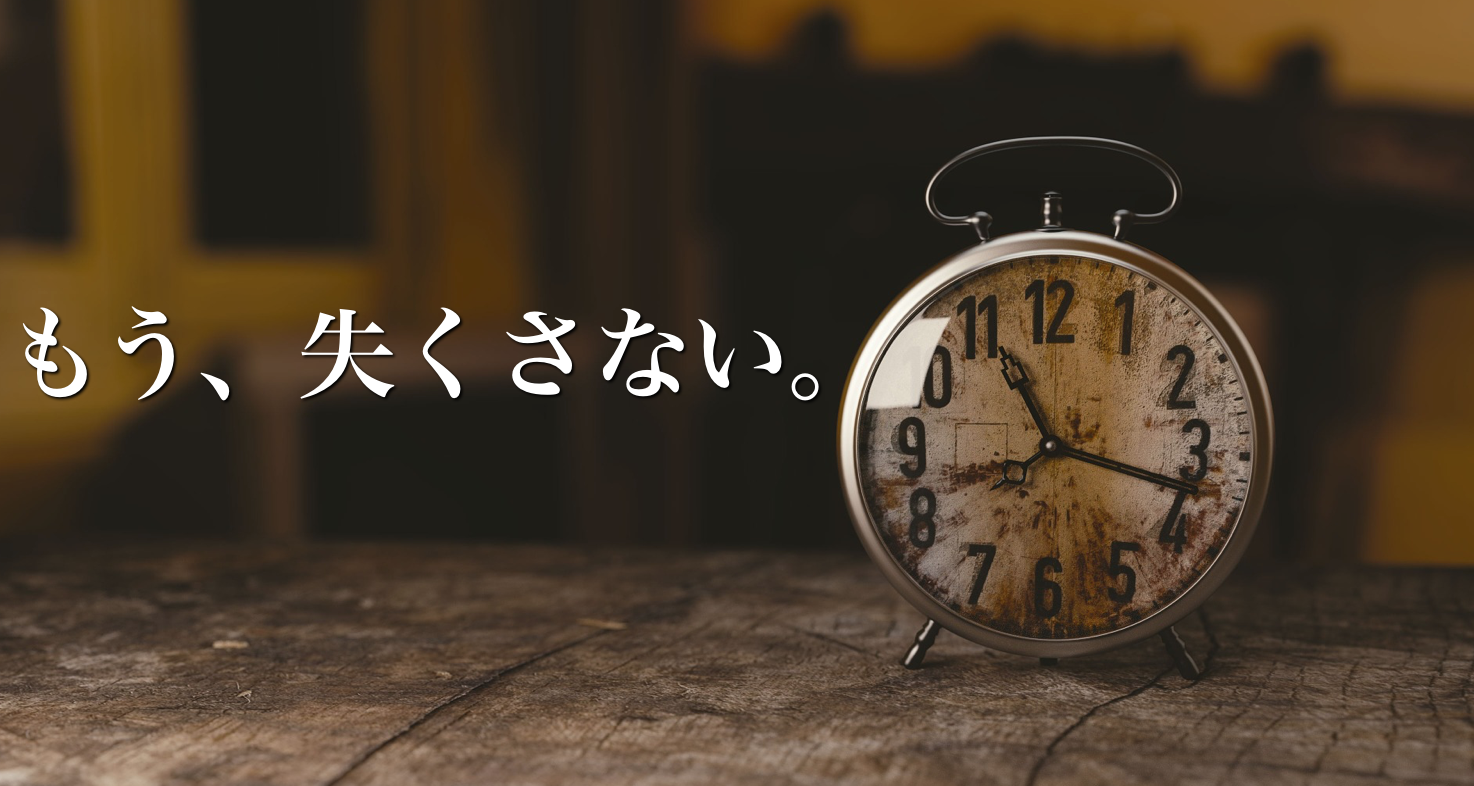
お疲れさまです。
今回は、
「よく物をなくす人」の特徴・性格と
4つの対策についてお伝えしていきます。
目次
大事な物をなくした…!?
先日、仕事で必要なものを取ろうとして財布を開けたら、違和感を感じた。
(何だ・・・?)
数秒後、違和感の正体に気付いた。
「免許証がない!」
その瞬間に、「様々な想定パターン」が頭に浮かぶ。
- デスク周りにあるのではないか
- カバンの中にあるのではないか
- やっぱり財布の中にあるのではないか
- 部屋の中の思わぬ場所に落ちているのではないか
1つづつ、確認していく。
ない。
この瞬間に
「免許証をなくした」という事実が確定する。
やってしまった……。
しかも、仕事の手続きで必要なのに。
貴重品をなくすなんて、何年ぶりだろう?
さて、どうすべきか…。
物を無くしやすい人の特徴
- 物を置き忘れる
- 落とし物をしてしまう
- 仕事に必要な物を持っていくのを忘れる
- 大事な物ほどなくしてしまう
原因のパターンは色々あるが、
起こる事象としては「紛失」である。
最近のニュースだと、
兵庫県尼崎市の業務委託先の関係社員が、
全市民約46万人の個人情報が入った
USBメモリーを紛失して大問題になっている。
特になくしやすい物は…
- 財布をなくす
- 携帯・スマホをなくす
- 鍵をなくす
- 帽子をなくす
- 書類をなくす
特に「財布」「鍵」「スマホ」などの貴重品、
「仕事の大事な物(書類・データ・制服・作業道具)」など、
「それがないと立ち行かなくなるもの」をなくすと、
自分だけではなく、
周囲も巻き込んだトラブルに発展してしまう。
また、こういった失態が度重なると、
周囲から
「同じ失敗を繰り返す人」という評価をされ、
仕事や人間関係において、最も大切な「信用」を失う。
必然的に、
「職場」や「人間関係」で苦しい状況に追い込まれてしまう。
なくした当人には悪気はないので、辛いところです。
ただ、
悪気はないんだけど、「原因」はあります。
まず、
同じことを起こさないために、
その原因を明確にしていきましょう。
大丈夫です。
こういったミスは、
「自分の意識」次第で未然に防げます。
「物をなくす癖」も、
要は「意識の使い方」の問題なんです。
「よく物をなくしてしまう人」の性格とは?
人はなぜ、物をなくすのか?
なぜ、自分が置いた物を置き忘れてしまうのか?
何が「物をなくさない人/なくしやすい人」を分けるのか?
「すぐ物をなくしてしまう人の性格」を解説していこう。
①そもそも意識して覚えていない
すぐに物をなくしてしまう人は、
そこに物を置くことを
「明確な自分の意思」で決めていないのだ。
漫然と行動し、無意識に物を置いている。
なんとなく、
ぼんやりと、感覚だけで行動している。
人間の行動の多くは、
その人の「動作のパターン」が
習慣化されたものである。
たとえば、
自分が経験を積んで慣れている作業は、
あまり思考しなくても感覚で出来たりする(ルーティンワーク)
毎日のようにしている行動ほど、
注意深く観察せず、感覚で動いてしまう。
だから、
後から物をなくしたことに気付いても、
どこに置き忘れたのかを
思い出すことが出来ない。
「そもそも意識して覚えていない」のだから、
思い出せるはずがないのだ。
②意識が「冷静な状態」ではない
慌てていたり、イライラしていたり、
焦っていたり、ストレス状態であったり、
他のことで頭がいっぱいになっていたり・・・。
自分の意識が
「冷静ではない状態」だと、
当然、注意力が低下し、
物をなくす原因になりやすい。
特に、
「過度なストレス状態」の場合、
「集中力」「判断力」
「記憶力」などが下がるので、
あらゆるミスが起こりやすい。
実際、
私もサラリーマン時代に経験したことがある。
職場の環境や対人関係で
極度のストレスがかかり、
心が疲弊していく中で、
自分で自分が信じられなくなるような
「凡ミス」を連発した時期があった。
「俺は頭がおかしくなったのか?」と
愕然とするような、
ありえないような単純ミス。
そして、
ミスをすることによって叱責を受けたり、
自責の念にかられたり、後悔をしたり、
ミスによって
「新たなストレス」が発生し、
そこからまた悪循環に陥ってしまう。
では、どうすれば?
「物をよくなくす人」4つの対策方法
①常に「冷静で落ち着いた意識」を保つ
何をするにも、
「冷静で落ち着いた意識の状態」
これが基本。
どんなに小さな変化や違和感にも気付ける、
澄み切った雑念のないクリアな意識。
理想は、
『明鏡止水』の境地である。
特に、貴重品を取り扱ったり、
重要な業務を行う時は、
自分の意識が
「冷静な状態」になっているかを、
自己観察してみよう。
「冷静さを欠いている」
「感情的になっている」
「疲れている」
「気が散っている」などと感じたら、
普段以上に注意深く行動し、
後確認を怠らないように気を付けよう。
心の中で
「ここに書類を置いた」などと
発言するのも良い。
自分の行動を「言語化」すると、
やったことを忘れにくくなり、
忘れても思い出しやすい。
ちなみに、
私がクライアントから受ける相談で、
「よく仕事に必要な物を持っていくのを忘れるんです」というのがある。
しかし、
詳しく話を聞いてみると、
「当時の朝にギリギリの時間で、慌ただしくバタバタと準備して出勤している」という場合が多い。
いつも、
「うん、それはフツーに忘れますね。」と答えている。
(ちゃんとその後にアドバイスしています)
私が会社員時代
「ミスをしやすい自分」から
「ミスをしない自分」に成長できたのは、
『仕事は「理詰め」で行うもの』
ここに気付いたことが大きい。
「クリエイティブな仕事」は、
感覚や感性が求められるが、
それ以外の、たとえば
- マニュアルや手順が決まっている仕事
- 業務連絡や手続きの多い仕事
- (事務などの)数字を扱う仕事
- 責任・プレッシャーがかかる仕事
- ミスが許されない仕事
- 常に「その場の判断」が求められる仕事
- 医療関係
そういった業務を行う時は、
徹底的に論理的に、理詰めで行うこと。
感覚に頼ってやってしまうと、大体失敗する。
「仕事の実力のある人」が
感覚で仕事をやれてしまうことはあるが、
それは「理詰めで仕事をした経験」の
膨大な蓄積があるからである。
②置き場所を決める
外出時に物を忘れたり、
探し物が見付からず、
いちいちデスクやカバンの中など、
部屋内のすべてを探しまわるのは、
そもそも、
「置き場所」を明確に決めていないから。
たとえば、
「スマホは必ずカバンのサイドポケットに入れる」と決めておく。
「財布は、必ずズボンの左ポケットに入れる」
「電車の切符は、必ず財布に入れておく」
「テレビやエアコンのリモコンは、必ずテーブルの上に置く」
また外出の際も、
バッグ内の「所持品の収納位置」を決め、
「このポケットにはこれ」と決めておくだけで、
紛失率は大幅に低下する。
「よく物をなくす人」は、
物の「置き場所」が毎回コロコロ変わる。
自由過ぎるんです笑
それだけコロコロ変われば、なくさない方が難しい。
私の会社員時代、
作業現場の車両庫内では
「すべての道具の置き場所」が決まっていた。
「使いっぱなし」
「置きっぱなし」は許されない。
どんなに小さな道具でも、
紛失すると大問題に発展する。
道具を使う前に
「所定の場所にあること」を確認し、
チェックリストに「レ点」を記入する。
道具を使い終わると、
最後に道具があることを確認し、
再度チェックリストに「レ点」を記入する。
すべての道具の
「置き場所」が決まっているので、
道具を探す必要性がなくなり、
作業時間の短縮にも繋がる。
自宅でここまでする必要はないが、
ある程度の「置き場所」は決めておいた方がいい。
物の整理整頓にも繋がるので、
掃除がしやすくなるのも利点である。
③スケジュール帳やメモ帳を活用する
忘れっぽい性格の人には、
メモや手帳を使った
「忘れ物対策」が非常に有効である。
必要なことは簡潔に
手帳やスマホでメモを取り、
その都度確認すること。
私の場合、
スマホのスケジュールアプリを活用している。
これはもう、
全ての社会人がやった方がいいです。
「Googleカレンダー」や「
Jorte Calendar」がお勧め(私はJorte Calendarを使っている)
何か予定が入ったら、
すぐスケジュールアプリに入力するといい。
「ポストイット」などの付箋を使うのもいい。
「小さなタスク」や
「忘れてはいけないこと」を
ポストイットに書き込み、
デスクやノートパソコンの隅に貼っておく。
ちなみに、
緊急事態で余裕がない時は、最悪、手の平に書いたらいい。
私も昔やったことがあります笑
自分の行動を把握できていれば
「無意識の行動」が減るし、
後から、自分の行動を思い出しやすい。
万が一、
物をなくした場合でも
「どこでなくしたのか」を思い出しやすい。
記事の冒頭で書いた
「免許証をなくした」の続きですが、
家の中を探して見付からず
「紛失した」ということが確定すると、
すぐにスマホのスケジュールアプリを見た。
この1週間、
市役所や銀行で、
免許証を提示する機会が2〜3回あった。
「最後に免許証を使用したのは、いつだろう?」
ここで
「3日前にコンビニで免許証のコピーをとった時」ということが判明した。
すぐにコンビニに出向き、
店員さんに「免許証の忘れ物はありませんか?」と聞いてみた。
あった。
その瞬間の
「テンションの上がりっぷり」といったら!
(なくしたの自分なんですけどね…)
自分のスケジュールを把握していたおかげで、
「免許証を再発行しに教習所まで行く」という
「最悪のケース」から挽回することができた。
④後確認をする(最重要!)
貴重品を取り扱う時や、
重要な業務を行う時は、
「後確認」を行うことを
習慣化しておこう。
「指差し確認」
「声出し確認」などが効果的である。
後確認は「忘れ物に気付く最後のチャンス」「ミスに気付く最後のチャンス」である。
「注意一瞬、怪我一生」の標語の通り、
後確認の重要性について、
多くの人が意識的になるべきだと思う。
「後確認を1回したら、ミスの可能性が30%下がる」くらいに考えた方がいい。
できる内は、何度でもやってもいい。
後で痛い目に遭うよりマシです。
「なくしものが多い自分」を卒業しよう
物をなくして、ミスをして、
結局後悔するのは自分自身。
常に、漫然とした
「無意識の行動」を
とらないように気をつけていきましょう、
そして、最後にお伝えしたいことは、
「物をなくしても、そこまで落ち込む必要はないよ」
数年前に、
東京で財布をなくしたことがあった。
7万円の現金、
新幹線の切符、
8枚ほどの銀行やクレジットカード類、全てをなくした。
帰りの新幹線にも乗れない。
「どうやって帰ろうかな…」と、一瞬途方にくれたが、
すぐに、
「厄払いできた」と思って仕切り直した。
(その後、東京在住の知り合いに連絡をして、お金を貸していただいて事なきを得た)
財布がなくなったら、また買えばいい。
カードがなくなったら、再発行すればいい。
仕事でミスをしたら、挽回すればいい。
それらは「自分の努力で取り戻せるもの」である。
しかし、
失敗を悔やみ続け、自分を責めて苦しんだり、
「自分には能力もない、価値もない」と自己否定しながら過ごしている時、
あなたは「自分の時間」をなくしている。
人生において「時間」こそが、最も大切な資産なのに。
それでは、本末転倒なんです。
『何があっても、私は大丈夫』
そうやって、
おおらかに、大きく構えていきましょう。